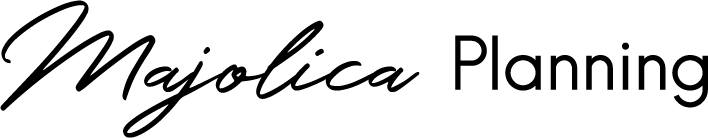2025.04.02ツアーレポート
千葉旅安房忌部ミステリー〈三神たける〉


今回のテーマは「神道、神社の祭祀をすべて取り仕切る忌部一族です。忌部氏は平安時代、藤原氏中臣氏に追いやられ、祭祀の実権を奪われていきました。しかし実際に神道の儀式、陰陽道も含め、色々なものを用意したり現場で取り仕切るのは忌部氏です。忌部氏の話は有名な斎部広成の「古語拾遺」の中にたくさん出てきます。

元々は古代天皇の儀式、祭礼を行わなくてはいけないと意味で、忌部氏のトップが天皇という位置付けもあります。祭祀を行うにあたっては、多くのものを用意しなくてはいけない。建築(神社そのもの)、作物などのお供物、かわらけなどの容器(土器)、儀式に使用する幣(ぬさ)、木だとか紙だとか一切合切用意する作るのが忌部氏です。ある種のテクノクラートとも言えますが、それらを管理するために全国に散らばっていきました。

元締めは当然ながら天皇なので、大和朝廷においては奈良県の大和盆地が拠点です。飛鳥地方には忌部神社があり、もとの神様は「アマノフトダマノミコト」太い玉(タマ・ギョク)。玉は三種の神器の勾玉のこと。そういった神器を司どる立場で天皇の周囲にいるのが忌部氏です。

そして忌部の最大拠点が海を挟んだ四国徳島(阿波忌部)。徳島の阿波は事実上忌部の拠点です。阿波忌部の三木家が大嘗祭で供える麻織物「麁服(あらたえ」をつくる。この麁服がなければ天皇は即位できない。実は議論があって実際は「麻」は「梶(かじ)」だと。これは木綿とも違って木の肌を叩いて漉いてつくる衣のことです。

他にも紀伊忌部、筑紫忌部、出雲忌部と、主に古いのは西日本です。これらはすべて「古語拾遺」の中に書いてあります。拠点は阿波でそこから移動していく。だから徳島特産の緑色の石「緑色結晶片岩」が各地で出土されています。この石が出てくるところは忌部族が行ったところです。

阿波忌部が西日本の支配を一段落すると次は東に向かいました。四国から紀伊半島、東海地方、静岡伊豆、そして千葉房総へ、その先にある「安房」は元々は四国の「阿波」です。「白浜」も同じで、紀伊の南紀白浜、千葉の白浜。民族というのは集団で移動して、かつて住んでいた土地をそのまま地名にします。物部氏もそう。その地に住んだ人たちが地名を名乗ってそれが名字になります。

特に関東の場合は、上総、下総の「総」も「麻」。麻布、浅草など忌部が関東に進出し麻を植えたからです。麻を植えて紙、衣服、護摩にも使われていく。アマノトミノミコトが忌部氏を率いて千葉にやってきました。トミは鳥のトビ、祭祀の人たちは鳥の称号を持つ。同族にアマノヒワシノミコト、こちらは鷲です。

https://youtu.be/HUxQwcOrTsY?feature=shared
訪問場所
高家神社(たかべじんじゃ)
下立松原神社(しもたてまつばらじんじゃ)
布良崎神社(めらさきじんじゃ)
楫取神社(かじとりじんじゃ)
安房神社・忌部塚(あわじんじゃ)
船越鉈切神社(ふなこしなたぎりじんじゃ)
海南刀切神社・海蝕洞窟(かいなんなたぎりじんじゃ)
洲宮神社(すのみやじんじゃ)
洲崎神社(すのさきじんじゃ
船形山 大福寺 崖観音
金谷神社 大鏡鉄(かなやじんじゃ だいきょうてつ)
予告
2025年6月14日(土)日帰りツアー
9月28日(日)お誕生日会
11月14日〜16日 ミステリーツアー

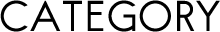
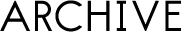
月を選択
- 2026年2月 (1)
- 2026年1月 (1)
- 2025年12月 (3)
- 2025年11月 (1)
- 2025年10月 (3)
- 2025年9月 (1)
- 2025年7月 (1)
- 2025年6月 (1)
- 2025年5月 (1)
- 2025年4月 (1)
- 2025年3月 (1)
- 2025年2月 (1)
- 2024年12月 (2)
- 2024年11月 (2)
- 2024年10月 (4)
- 2024年8月 (7)
- 2024年7月 (1)
- 2024年6月 (1)
- 2024年4月 (1)
- 2024年3月 (1)
- 2024年2月 (4)
- 2024年1月 (2)
- 2023年11月 (5)
- 2023年10月 (2)
- 2023年9月 (5)
- 2023年8月 (2)
- 2023年6月 (1)
- 2023年5月 (3)
- 2023年4月 (3)
- 2023年3月 (1)
- 2023年2月 (6)